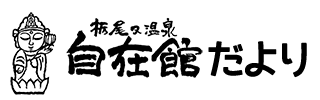最近、Amazonのおすすめアルゴリズムに引っかかり、ふと手に取った本——『「怠惰」なんて存在しない 終わりなき生産性競争から抜け出すための幸福論』。
さすがAmazon、私たちのことをよく理解していらっしゃる(笑)。
この本を読んで、「休んではいけない」「勤勉でなければならない」という強迫観念は、日本人特有のものではないのだな、と感じました。登場人物の名前が日本人名だったとしても、まったく違和感なく読めてしまう内容。これは、ある程度の経済成長を経験した国ならではの現象なのかもしれない、と改めて考えさせられました。
もちろん、この本を読んだ方の中には、「とはいえ、皆が怠惰を肯定してしまったら社会が成り立たないのでは?」と批判的に考える方もいるかと思います。しかし、大切なのはバランスです。怠惰とは、バランスが崩れていることのサインであり、それを適切に受け取り、活用することが必要なのです。決して、「怠惰が絶対的に正しい」と主張しているわけではありません。(たぶん。)
努力することや頑張ることは素晴らしいことですが、それを悪とするような二極論ではなく、「頑張るタイミング」と「休むタイミング」のバランスを見極める力が大切だと感じます。そのためには、「疲れた」「怠い」「やる気が出ない」といった体のサインを無視せず、自分自身の疲労度や精神状態を適切に把握することが重要です。
「疲れた」「怠い」「やる気が出ない」は、決して悪いことではありません。これは、600万年の人類史の中で、生き延びるために獲得してきた大切な能力の一つ。たとえるなら、車のセーフティーセンサーのようなものです。センサーは進化し続け、より安全で快適な運転を可能にしています。それと同じように、私たちも自分の限界を察知し、適切にブレーキをかけることが必要なのではないでしょうか。
一方で、「もっと成長したい」「もっと上手くなりたい」「もっと手に入れたい」といった“もっともっと”系の欲望も、人類が生存競争の中で獲得してきた機能の一つです。この欲望のおかげで、今の文明があることは容易に想像できます。しかし、この機能もまた「使い方」と「バランス」が大切です。
再び車の例えでいえば、スピードがどんどん出せる車があるとしても、無制限にアクセルを踏めば危険が伴うのと同じです。一定レベルまでは便利で快適ですが、度を超えれば事故のリスクが高まり、命を落とすことにもなりかねません。特に、人が多く行き交う街中では、猛スピードを出せば周囲と衝突する危険が増します。現実の社会でも、私たちは多くの人と関わりながら生きているのですから、自分の欲望のまま突っ走るのではなく、外部とのバランスを見極めながら、快適なスピードをコントロールすることが大切だと思います。
さらに厄介なのは、この“もっともっと”の欲望には際限がないことです。これは、キリスト教では「大罪」、仏教では「煩悩」とされ、他の宗教でも「制御すべきもの」として長く語られてきました。まさに「言うは易く行うは難し」。昔から分かっていながらも、人間が完全にはコントロールしきれないものなのかもしれません。
だからこそ、豊かな人生とは、「もっともっと」と欲望に身を任せるだけでなく、かといって怠けすぎるわけでもなく、そのバランスを保ちながら生きることなのかなと思います。そのバランスは人によって異なるでしょうし、どれが正しいということもありません。結局は、自分自身を深く見つめつつづけることが、とても大切なことなのだと思います。